あの組曲
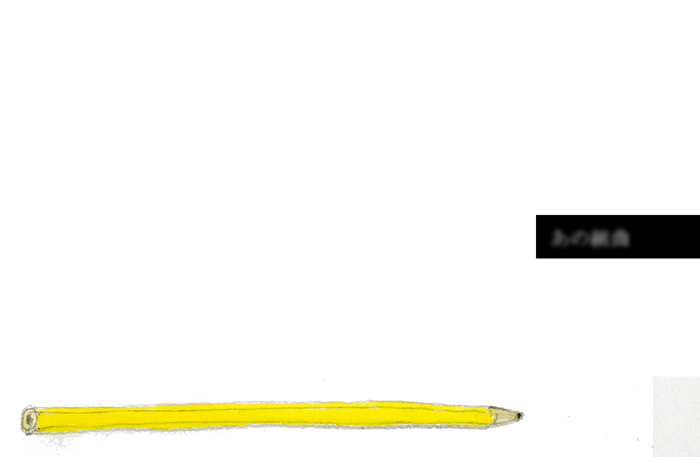
もうすぐ深い霧に包まれることを動物達は知っていたようで、うきうきとしたような、そわそわとしたような、足音や息遣いがその大きな沼の周りに満ちていました。
やがて名も無ければ顔もない指揮者が息を止め、その場に居合わせた様々な形をした者達のざわめきが引いて、彼らの謙虚で無垢な視線が尖った指揮棒の先に集中する。
若い鹿が祈るように黒い瞳を閉じた瞬間、冷たくて豊かな霧が湧いてきたのでした。
後部座席で毛布にくるまっている彼女は細く開けた窓から、白い空気の流れを見ています。
一つ残さず濁りの消えた目に、誰のものとも知れぬ感情を湛えて。
ぼくはまだ、眠ったふりをしながらルームミラー越しに見ていました。
もし、たとえ、そのときのぼくが彼女の身と心に起きようとしていることを知っていたとしても。
もし、たとえ、そのときの彼女が彼女の身と心に起きようとしていることを知っていたとしても。
ぼくは眠ったふりをしながら、彼女のことを見ているだけで。
彼女は冷気に頬を晒し、毛布を顎の辺りまで引き上げるだけで。
彼女が吹いたしゃぼん玉は、虹色に揺れながら濃い霧の中に消えて行く。
時の中へと消えていく。
その頃のぼく達のことはうまく思い出せません。
そんなに美しいことばかりではなかったはずだと思います。
言葉も、論理も、語尾も、汚く。
過剰で、言葉足らずで、平凡で、幸福で。
ぼくもにして、彼女にしても。
そう思えば思うほど、うまく思い出せない。
もしかすると、あれはぼくたちの未来のことだったのかもしれないとも思うし、
未来のぼくたちの記憶だったのかもしれないとも思う。
あるいは、今の自分だって未来のぼくの回想かもしれない。
あるいは、未来の彼女の回想なのかもしれない。
ぼくたちは決して良いことをしてはいないのでしょう。
もう死んでしまった人のことを、まるで生きているかのように振舞わせたり。
まだ生きている人の五本の指を、まるで死んでしまったかのように組ませたり。
そういうことだけはしてはいけないと、言われる類のことなのでしょう。
ぼくはまだ眠ったふりをしながら、ルームミラー越しの彼女から目を離し、時計に目をやる。
デジタルの黄色い光が示す午前六時前。
永遠の午前六時前。
もう後部座席に誰の姿もありません。
今朝は霧も出ません。
色濃い緑が沼を囲みます。彼女の成分と、この景色の成分は同じです。
水面から顔を出している細い枝も、危うく沼に崩れ落ちそうになっている枯葉の山、姿を見せず陰気に鳴く鳥や、錆びて朽ち果てたガードレールも、蜘蛛の巣も、彼女を構成したものはすべて、今はこの沼に還りました。あそこで朝の六時前から石や枝や木の実や思い出や言葉や淋しさや不安や強がりや正直さを沼に投げ入れて、水中の生き物の眠りを妨げるこどもたちもまた、まぎれもなく君と同じ成分でできている。
チェロのふくよかな旋律に彼女の上手なしゃぼん玉は大きく膨らんでいく。
やがてそれは沼を覆い、見上げんばかりとなり、こどもたちを夢中にする。
触りたいけれど触ると割れることを彼らは知っている。
触らなくてもいつか割れることも彼らは知っている。
目を輝かせて巨大なしゃぼん玉を見上げている。
いつの日か君たちにも訪れるだろう。
そのしゃぼん玉を割らない方法を知る日が訪れるだろう。
ぼく達は君達にそれを望まないような、けれど、知って欲しいような気もする。
いずれにせよ、まだずっと未来の話だ。
今はただ、彼らの投げた小さな石が、沼の底に優しく舞い降りて美しい煙を上げる。
空にはまだ何の予兆もない。
未来の予兆はない。
すべては君たちと、ぼくと、彼女の未来。
他の誰のものでもなく。
彼女がぼくたちの前から去り、一年が経過しました。
一年を百篇の詩で数えてみるけれど。
その詩は、ぼくが書いた詩ではありません。
生前の彼女が書いたほんの少しの詩と、生きていた頃の彼女を模してぼくが書いた詩です。
図らずも、百日を数えるつもりが、もっと多くの時間を遡って数える結果になりました。
詩人であるぼくのことをいつも読んだ、誰よりもぼくの詩を知っている彼女の書く詩は、ぼくの詩に似ているでしょうか。
あまりぼくの詩には似ていない気がします。
何よりも、詩人らしくありません。
詩人らしくないなんて、なんて素敵なんだろう。
ぼくは憧れの中で模してこれらを書き、これを編みました。
彼女が、彼女の生きた時間と、いない時間の境目を詩にしてくれた。
詩という、言葉を水に溶かしたような、その原型をとどめないものにしてくれた。
世界は何も変わっていないということを、彼女は言っているような気がした。
それが本当かどうかなんて、どうでもよかった。
何かが、本当かどうかなんて、本当にどうでもよかった。
思い出すのではなく、その瞬間その瞬間に水に溶けた言葉を辿っていく。
傷ではない。棘ではない。落書きだらけの心の壁の前で眠り、拾った貝殻を耳に当て、時間は壊れてはいないし何も変わってはいない。何もかもがあの頃のままなのだと、彼女が言っているような気がした。
ぼくは半信半疑というか、何というか。
だって、ぼくはまだ死んではいないから。
あの電話 受けたあの日の あの場所の 歩道橋の 色が違う
あの子は だれかが こぼした蕎麦を 片付けたんだ
しにたくないと 言っていた しにたいと 言っていた
水という 字で埋め尽くされた 恋の気配
返事でも 嘘つく彼の ドアの音
さようなら 肌色の人 さようなら
タワレコの みんなが着ている ポロシャツを じっと見ている
タワレコの ポロシャツ脱いで 抱き合えば どっちがどっちのポイントカード
ぼくのつくえは安いので ずっと揺れてる 頬杖をついても 揺れてる ほんとに
彼女が言った「なるほど」 とても素敵な 世界で一番の 「なるほど」
Ⅰの話
歩道橋の歌は、記憶の中の歩道橋の色と、たまたま再訪したその歩道橋の色が違っていたという、それだけの詩です。この詩は何度かメロディに乗せて歌われたこともあり、(彼女の詩の中では)有名な詩ですが、「あの電話」が何の電話だったのかは、最後まで明らかにされませんでした。およそ不吉な電話だったのだろうと勝手に考え、幾つか心当たりをぼくは想像しています。
ちなみに、ぼくにも似た経験はあります。
真昼間からスーツ姿でアイスクリームを食べていました。
コンビニの前に日陰が無かったので、近くの歩道橋の下でアイスクリームの包装を開け、一口も食べないのに、鞄の中のケータイが鳴りました。やばい。サボってるのがバレると思って(バレるわけがないのに)、慌ててケータイを取り出します。それは会社からではなく、懐かしい友人からの電話でした。そこでぼくは共通の友人が死んだことを知ります。電話口ではっきり聞いたわけではありませんが、それが自殺だということは分かりました。口ぶりから分かるものです。
なぜどうしてと問わないならば、いつもとても電話は短く。
味もしない、冷たさも感じない、なんてことはありません。みるみる溶ける、甘いアイスクリームをぼくはバカみたいな顔して、歩道橋の下の狭いスペースでだらだらと食べていました。歩道橋の色は緑だったと思います。
誰かがこぼしたそばを片付けるエピソードは、ぼくの中ではとても大切なものです。その頃ちょうど足を怪我していた彼女が、人で溢れかえる満席の学食でようやく空いてる席を見つけたところ、派手にそばがこぼれていたのでした。
なるほどが今も耳に残る。
なるほど
口笛の 下手なあの子は 泣き方も 上手くはないけど ないけれど
ルパンのエンディング? そう おねがい と言われても
大切にしてきた金と銀との折り紙の束 持ち寄りぼくらの暮らしが始まる
あんときの 子供らがもう 月行って帰ってきよった なんもなかいうて
テレビ見て 怒る君の横顔を 嗚呼、ぼくが怒られなくて ほんとによかった
折り紙の ツルをこどもに 教えてる あなたの声を 持ち歩く
エルグランドと エルグランドの間の 細い狭間で聞いた 「統合失調」
臆病者が 思い出の意味も変えていきます 嫌々
いじめられっこ 分解している 三色ボールペン 何色だったら 読みますか
目を開けて 大丈夫だよ もう過ぎた きみが嫌いな ラブホテル
Ⅱの話
ルパンのエンディングと言われれば『愛のテーマ』がすぐに流れるような、海沿いが二人の希望だった。
簡単なことだから、希望はちゃんと叶う。
ぼくたちの結婚生活は、沿線の片隅で、しかも住宅地の外れで、その上マンションの隅っこで、だけど海沿いで、ごくごく平凡に始まりました。
作りはリゾートマンション。時代遅れの内装と、一年を通して穏やかな海。
貝殻を拾って帰るようなぼくたちではなかった。
吸殻を砂浜に捨てるようなぼくたちではなかった。
あそこに住んでいた時は一度も泳いだりしなかった。
泳いでいる人を眺めながら、今日は詩人らしいこと言える? と彼女が言う。
今日も何も浮かばない、とぼくは答える。
明日も明後日も。
ここでは海に背を向けている人はいない。
みんな街に背を向けていた。
愛を胸に抱いて ふるえて眠れ
詩人の端くれとして、他人の詩を誇らしく思う。
根気よく折鶴をこどもに教えている、君の教え方があまりに優しくて素敵だったのでぼくは録音した。
折鶴を教えてくれる人は、人生に何人も現れない。
それにしても、こどもたちが生まれ、折り紙三昧の日々がやってくるのは、もう少し先のはずなのに、もしかしたら月に行って帰ってきたら、時間がおかしなことになっていたのかもしれません。
だとしても、もうどうしようもない。
ぼくは今、過去にいるのかもしれないけれど、彼女がこどもたちに折鶴を教える姿を知っている。
まるで、それは夢で、嘘みたいだ。
ほんとに、ぼくらにそんな時間が訪れるのだろうか。
言葉が乱れるのは、感情が乱れているからではなく、時間が乱れているからだよ。
ほんとに、そうだね。
なんだかんだ言ってあれから一度も聴けない折鶴の録音。
こどもたちはもう聴かなくたって上手に折れる。
もしかしたら、いつか彼らにもこどもが生まれる日が来たら、その子達が聴くのかもしれない。
会ったこともない、ピンとこない、若いおばあちゃんの声を。
落ち着いて、ゆっくりやりなさいと。
泣き止んだ時は 溶けたチョコレートでも 食べるでしょ そんな気持ちでいたい いつでも
プライドと 甘えだけかと 思ってた
ストップ 短い絶望 多いと良くない
飲みたかったわけじゃない 渡り廊下の七十円は おこづかい
トゲザー ラヴトゲザー そんな日もあるトゲザー 信じてなくてもいいトゲザー
「一緒に逃げよう」 よく知ってるね 信じなくてもいい類の 言葉を
いまさっき 帰った彼女から電話 元気な声の 「アンドモア!」
「やめさせよう」 ニュースを消して 飛び出した 深夜の助手席 淋しいハイウェイ
店主無き かき氷屋の 行列に 並んでみたら いいんじゃない?
あなたとわたしを区別する たったひとつの 名前も替えたい
Ⅲの話
今では訊ねられることも少なくなったが、それでも稀に、若い人が多いだろうか、どうしてかを問われることがある。
どうして?
どうして詩なんて書いているのか。
どうして書き始めたのかを答えるのは歴史的事実で比較的簡単だが、どうして書き続けているのかに答えるのは難しいし、その難しさについて説明することも、とても難しい。
およそ質問の向きとしては、書き続ける理由を問われる方が圧倒的に多い。
ほとんどがそうだ。
どうして(いつまでも)詩を(詩なんて)書いているの?
ぼくは答えてきた。
その質問の意味するところが、「どうしてたいして良くもないのに」、いや「まったく良くないのに」どうして書き続けているのか、どうして書き続けていられるのか、というものだとしても。
それなりに答えてきた。
もう忘れてしまった。
どうやって答えてきたのか。
ぽっかりと忘れてしまった。
書き続ける理由は忘れてしまったけれど、そのことが書くことをやめる理由にはならないだろう。
プライドと甘えだけかと思ってた。
「それを言われた時の男の人の反応で、大体のことはわかる」
そんな乱暴なことを言う女の人と食事をして帰った夜、彼女にそのことを話した。
彼女は、その人の言ってることは当たってると思う、と言った。
そして背中を向けると、プライドと甘えとわたしだけかと思ってた、と言った。
午前二時 トイレの電気の消し忘れ 愛しさ返す 消さない光
いりこのね おなか開いてたら急に 水が出てきて 産院へ
おかしいかなとぼくがいう なにがととぼける彼女の右手
天気雨 途切れ途切れのピアノの練習 そうだ 今日は彼の命日
事実上の解散は 空想上の永遠で 空想上の事実は 事実上の空想だ 愛してる
リフレインは叫ばない もうリフレインは叫ばない いつからだろう叫ばない
助手席で 眠って起きたら 山梨県 二人の知らない 道でおはよう
オウンゴール! 叫んだ友の今日を褒め 辿る家路で 真似をしつ
しあわせは きみの机の 消しカスの山
思い出す もう忘れたという歌を
Ⅳの話
いりこのおなかを開いてたら水が出たと電話がかかってきて、急いで帰宅した。
雨が降り始めていた。
公園の森も煙る春の雨。
薄暗いキッチンにきみはいた。
取り急ぎの着替えだけ鞄に詰め込むと、タクシーを呼んで病院へと向かう。
ワイパーは激しく雨を払った。
救急の受付を済ませると、待合のベンチに座っているように言われる。
この時のぼくたちは、何も知らなかった。
何も知らず、待合いの自販機を眺めていた。
唸り声を上げる自販機の前で、ぼくも彼女もとても静かな気分だった。
彼女は普段とあまり変わった様子はなく、ほんとうに急に水が出たのよ、と愉快そうに言った。
後になって、ぼくたちは知った。
笑いながら待っていたその時間も一分一秒を争う危険な状態だったということを。
知らなかったぼくたちは、並んでジュースの自販機を見ていた。
看護士の押す車椅子に乗せられエレベーターに消えた彼女に次に会った時には、もう手術直前で、既に麻酔が効き始めた彼女は、ぼんやりとした目をしていた。病室のベッドの上、淡いブルーの手術着の袖から血の気のない腕を出し、ついさっきまで笑っていたのとはまるで別人だった。よくわからない計器が彼女のなにかを計っていた。
なにを話したのか覚えていない。
雷雨になった。
病院の窓から見下ろす黒い屋根屋根を、狂ったように雨が洗っている。
それでも、ぼくには何の不吉な予感もなかった。
面会ルームの隅にはテレビカードの小さな販売機があり、テレビが好きな彼女のために一枚買った。
受付で並んで座っている時、彼女はキッチンのいりこの心配をしていた。
おなかを開けた分だけでも、使っちゃってね。
先に手術室から出てきたのは、こどもの方だった。
初めて会う彼は、見るからに甘えん坊な感じで丸くなってまだ目を閉じていた。
その夜自宅に戻ったぼくは、キッチンテーブルの上に放置されたいりこを、どうしていいのかわからず、袋に入れて暗い冷凍庫にしまった。
ぜんぶがぜんぶ割れるときにも あなたのだけは割れないように
白銀に 二本の轍と 足跡が行く どちらもぴたっとここで消え
風が怖い 波が怖いと泣く子らを テントの明かりで抱く二人
にじんだにじが訴える わかってる それは二人もわかってる
一本の 長い髪の毛 沈みだす
障子の向こう 君が鶴だと言うのなら ぼくも鶴だよ 仮病の鶴だ
点滴を 交換しに来た 看護士が 背けるくらいの 赤い目で
しゃぼん玉 当ててドラゴン倒すやつ 写真に撮った エンディング
星の下 ビキニの日焼け 朝露と消ゆ
みずうみに シャボンにも飽き 自分にも 欠伸見合わせ 飽き飽かずもがな
Ⅴの話
ミロンは水晶を取ったり、のこぎりを買ったり、井戸に入ったり、火のおばけの下を駆け抜けたり、茶色いもじゃもじゃのやつを倒したりして、一つずつ上の階へと進んでいく。
かつて、ぼくたちもこどもだった。
部屋の外に出れば、雷が降ってきた。暖炉の中に入ったりして。
来る日も来る日も、こどもだった。
ミロンは来る日も来る日も、退屈な一階を抜け、二階を抜け、三階で疲れ果ててしまう。
古本屋の片隅で、退屈していたぼくたちは色褪せた古いソフトに再会する。
ぼくも彼女も、ミロンのことを知っていた。
気の抜けるようなワルツに乗せて、ミロンはしゃぼん玉を吹いていた。
あれから二十年以上の時が流れ、ぼくたちは休日の夜を持て余していた。
まだこどもたちがやってくる前の話だ。
ミロンは、今もまだあの城を抜け出せずにいた。
ぼくたちはのめりこんだ。
ゲームなんてしないぼくたちだ。
のめりこんでも、あまりしないぼくたちだ。
たまにしても、たまにするだけのぼくたちだ。
そんなふうにやがて、しゃぼん玉の色を変え、ホバリングできるようになり、黒いやつも出てきたりして、たくさん音符を取って、オーケストラは完成して。
ベッドの上の彼女は、懐かしそうにその日の話をした。
エンディングのキャプチャーを取ったその日のことを。
一度きりの最終ステージだった。
ラストチャンスだった。
ミロンのしゃぼん玉は、憂うようにマハリトを撃った。
偽物のマハリトを、本物のミロンが撃った。
偽物のマハリトを、本物のミロンが撃った。
ミロンは目を閉じることなく、何一つ変わることのない心持ちのまま、今日で全てが終わることを知っていた。
二十数年にも及ぶ長すぎた迷宮も、あっけなく、短かった迷宮になってしまうことをミロンは攻撃をかわしながら感じていた。
激しい戦いの中、ミロンはこっちに手を振る。
あれからぼくたちは一度もミロンに会うことはなかった。
持ってこようか? と、ぼくは言った。
やめとく、と彼女は言う。
痩せたいなんて言ってたの、半年前のことなんだぜ。
痩せ細った指で、彼女はコントローラーを操作する真似をする。
あんなふうに、やっつけられたらいいのにね。
その頃から、彼女は本当によく泣くようになる。
ぼくがいない時も泣いていたのだろうか。
それとも薬のせいだろうか。
彼女の目は赤いことが多くなった。
こどもたちは、ママの目の色について何も言わない。
かなかなと ヒグラシ聴いてる きれいなおでこ
かなかなと ヒグラシ聴こえる おでこに耳あて
高級店 恥かいたこと 二人の思い出
ごめんなさい ほかの誰かと 過ごしたことさえ すべて 二人の思い出のようで
ベッドの下の 一度も履いてないスリッパを 季節に合わせて 変えようね
仕方なく いつもと違う 煙草開ける二人
図書館の本に引かれた傍線の 見覚えのある長さで午睡
あらゆるものが 君に似てくる その椅子も あのカーテンも この歌も あの戦争も
日本のウィノナ・ライダーになりたいと思っています
警官に引きずりおろされたあの屋根に 登って遊ぶ子供達
Ⅵの話
父も、母を若くして亡くした。
ただの偶然とは言え、数奇なものだと思う。
春になって新調された母のスリッパは、ベッドの下でいつも綺麗に揃えられたまま、一度も履かれることはなく秋を迎えた。冬のスリッパは買っていない。
春のスリッパをデパートに買いに行ったことを覚えている。
そのデパートも随分前になくなって、学習塾に変わって、今は空きテナントになっている。
父と母の真似をしたわけではないが。
大きなデパートの店員が苦労して包装したスリッパを持って行くと、彼女は喜んだ。
今になって思えば、縁起が悪い、ということになるのだろうか。
まさか、そんなわけがない。
なんにもわかっていない。
一度だけ父がお見舞いに来た。
その頃は、まだ病状も軽く、こんなことになるとぼくは重く考えていなかった。
でも、父は少し違ったようだ。
なんだか悪かったねと、よくわからないことを言って彼女を困らせたのだった。
日本のウィノナ・ライダーになりたかった女の子は、結局日本のウィノナ・ライダーになんかならなかった。
多くの女の子たちがそうであったように。
すっかりウィノナ・ライダーのことなんか忘れ、たまに思い出したりして生きていた。
ウィノナ・ライダーの名前の横に線を引いて生きていた。
こどもたちは彼女に似ていると思うか。
そうと聞かれるたびに、スリッパで頭をひっぱたいてやろうかと思うよ。
いつまでもいつまでも、いいかげんにしろと言われても、叩き続けてやろうかと思うよ。
黙って叩き続けて、蹴っ飛ばして、手元のグラス投げて割って、帰れと叫んで、まあいいや。
似てるに決まってるんだ。
どうしてスリッパで叩かにゃならんのだ。
下半身 すーっとしたので おねしょかと 思ったらただ泣いていただけ
きみの書く 少女みたいな 筆記体 書いてほしいな 二人の名前
グランドに伸びる 影踊る グリップの握り逆でも 誰もいてない 右中間
今は無き 銀行のキャッシュカードの 暗証番号みたいな 合言葉が あれば良かった
舞う雪が カーステレオから 事故渋滞 これは雪じゃない 雪のこどもだ
遅れてるスコールと特急列車を待ちながら 時報の前に 流れる歌
十年も前の そのことを 謝ってくれて ありがとう
質問をよくする女子としない女子 しない女子と過ごす夜
今週から テレビのチャンネルが ひとつ減ります そしてそのうちまたひとつ
光で出来た誕生日ケーキに きみの代わりに息をかけると
Ⅶの話
異国の駅で、貨物列車がのろのろと通過していく。
ぼくたちは疲れ果ててホームに座り込み、濃い影の中にいた。
貨物列車に満載されたコンテナには何がそんなに詰まっているのか知らないけれど、車輪は軋み、連結はがちゃがちゃと無感情に手錠のような音を立てていた。
首都へと戻る次の特急列車までにはまだ随分時間があった。特急列車とは言っても、エアコンもなければ、座席も固い木製。ところどころ窓が壊れていて、スコールが降っても閉じることができないような旧型車両。来た時と同じ、また二時間も、田園と熱帯雨林の中を揺られることになる。
疲れきったぼくたちは固い座席で眠るだろう。
街は暮れるだろう。
首都の光がぼくたちを迎えるだろう。
この田舎の駅で黄色い日差しに支配された風景を眺めていると、そんな都市はとても遠い空の下、どこか違う時空の、知らない人の人生のように思えた。
特急列車は予定よりも少し遅れていると、駅員がわざわざやって来て教えてくれた。
自信が無いのか、短い英文を中年の駅員は何度も繰り返す。不気味に綺麗な顔をしている。
地元の女の子がやって来て、彼女の隣に座った。物売りの子ではないようだった。
よく日焼けした、くたびれたグレーのノースリーブを着た地味な女の子。
中学生くらいだろうか。綺麗な英語を話す。
日本に行きたいのだと彼女は言った。日本語は話せないのだそうだ。
わたしとあなたで交替しないか?
と、少女は言った。
いいね、と彼女は言った。
いいけど、もう一人男の子を連れて来てよ。
彼女は黙って立ち上がると、駅舎の方へ歩いていく。どうやら改札を出て行ったようだった。
からかっちゃ可哀相。
先程からホームの端で中年男が弾いていた暗いラテンギターの音が止まった。
そして、高いところにあるスピーカーから管楽器の音。国歌か何かだろう。見回せば、直立で国歌を聴く人々。ぼくたち二人だけがだらしなく座り込んでいる。
すごすごと帰ってきた女の子は誰もいなかったのだと言った。
女の子がぼくたちに言った。
生きていればまた会える。
ディーゼルのひどい音の中で、ぼくたちは映画みたいに別れた。
「若い子にチェンジしたかった?」と、動き始めた車内で彼女は言う。
「それって、わたしが生まれ変わるってことかな?」と、彼女は言う。
「生きていれば、なんて、若いくせにね」と、彼女は言う。
「生まれ変わりを信じる国のこども達なのにね」と、彼女は言う。
「因果応報を信じる国のこども達なのにね」と、彼女は言う。
「わたし達がね」と、彼女は言う。
いつの間にか、ぼくたちは眠りに落ちている。
苔と羊歯 古い霧吹き こぼれるくらい
ビールの匂いをよく嗅いで 飲んでたあなたが えらい人
美声恥ずかし カラオケスナック あの日だけだよ 止まらなくなって
流星群 待つとき 雪崩を 待つとき 同じ前髪
一緒に謝りに行こう パパと行こう
見も知らぬ 旧街の声を避け巡り 沼の隣に 自転車を停めた彼が 君は好き
時には 思い出行きの さだまさしみたいになりたいねと言い お揃い眼鏡 買いに行く
いいやつと みなに言われる あのひとが きみのことを なんども笑った
かわいそうと いうらしい ほんとはそうじゃないらしい それでもやっぱりそうらしい
左の耳の 調子が悪い 左に立ってくれないか そして話してくれないか
Ⅷの話
わたしが死んだということにして。
そういうふうに、彼の死を扱うことに、後ろめたさはなかった。
それは、おそらく彼も全く同じことをしたのではないか、という身勝手な思いから来ている。
彼も、自分が死んだことにしたのではないかと思う。
わたしが死んだときには。
わたしは自暴自棄になる気も開き直る気もない。
しっかり生きようと思う。
わたしの死後、彼がしっかり生きたようにわたしもしっかり生きようと思う。
彼が思い出すくらいは思い出して、彼が忘れるくらいには忘れながら、しっかりと生きようと思う。
わたしは彼の真似をしている。
あんたは馬鹿だ。
ほんに馬鹿たい。
あいつが思い出したり、詩を書いたりしよるか?
せんせん。
せんね。
しよらんて。
新してしょうもなか女んとこ行きよる
なんだかんだ言い訳しよって、女んとこ行きよるよ。
自己否定と。
自己肯定ばっか。
ふふふ。
達者になった、あいつのことね。
あんたにそっくりな。
あんたの生まれ変わりみたいの探して。
本気であんたやと信じて。
あんたの生まれ変わり見つけて、同じこと繰り返しょる。
ちゃんとあいつは見つけよる。
正論なんて通用せんて。
あんたらには、あんたらのやり方がある。
続いてるストーリーがある。
うちらは知らんよって。
あんたら二人しか知らんよって。
あたりまえやん。
わたし達しか知らないこと。
わたしは、こども達に死ぬということや、彼のことをどのように教えればいいのか、考えるようになった。
教えられることは限られていた。
パパは、どうしてもきみ達と一緒にいたいと思っていたということ。
だからと言って、何かを恨んだりすることなく、とても静かに、幸せに死んだのだということ。
パパがどういう人だったか?
ママみたいな人だったよ。
あんた馬鹿か?
なして子供に嘘教えよる。
あんたと違うて、どうしようもないやつやったろ。
「ちょっと黙って。冗談でも許さんよ」
気付いても 悪びれもせず ぼくを見て きみはほんとにきみですか?
ほとんどの 宇宙から来た鳥 怖い鳥 ぼくらを見ている 白い鳥
午後の日差しが 床に落とす 平行四辺の明るい窓を あの子が塗って そんな記念日
約束は ぼくとぼくとの約束は きみときみとの約束は きみとぼくとで見た夢は
連弾で 弾ける曲がないならと 作ってくれたあの曲を 今日から一人で練習するよ
右耳の 調子も悪い 右に座ってくれないか あれを歌ってくれないか
てにをはと かかりとむすびを 見てくれた あの子の代わりと言うのなら 一緒にお風呂
きみの写真の飾られて 正座しているぼくなのに きみが隣でぼくをくすぐる
きみの名前の飾られた 狭いベッドに潜り込む きみをくすぐるわけでもないけど
喩え話をねだってる こども達には すべてをあげる
白い花 紫の花 青い花 それだったら 白い花
白い花 手にしたこどもが 飛び出して 急ブレーキのマイクロバスにも 白い花
Ⅸの話
大きな白い花を手にしたかわいいこどが二人、追いかけっこでもしていたのだろう、低い生垣の隙間から霊園の太い外周道路に飛び出したところに、ちょうどマイクロバスがやってきて、急ブレーキを踏んだ。幸いマイクロバスはスピードを落としていたので、こどもたちの手前で停車した。父親が飛び出してきて、運転手に頭を下げている。通り過ぎるマイクロバスの座席には、飛び出したこどもたちと同じ白い花を抱えた人々の一団。すっかり落ち込んだこどもたちを見ている。
きみの写真は飾られていたけれど、それはきみの葬儀じゃないみたいだった。
ぼくだってそう思っていたのだから、こどもたちなんてどう感じていたんだか分かったもんじゃない。
じっとしていられないこどもを言い訳にして、読経の途中で式場の外に出た。
長い尾をした白い狼みたいな、巨大な雲が空の端から端まで伸びているような、そんな快晴。
もうこのまま帰りたくなる。
いつだったっけ。
二人で参列した誰かのお葬式。大きなお寺で、パイプ椅子は老人達が使い、ぼく達は床に座っていた。痺れの切れたぼくの足を、きみはこそこそと突っついてくる。まだまだ長い式の最中だし、ぼくは目を白黒させて、やめるように手で払っていた。きみはお構いなしで、声を殺して楽しそうに。
あれは一体誰の葬儀だったんだろう。
と考えていた。
愛する人や動物が死んで泣かせるような映画を観たり、そういう本を読んだりしても泣くようなタイプではなかったぼくは、友人達から冗談交じりではあるけれど、血も涙もない人間だと言われてきた。
でも、彼女の葬儀で涙一つ見せないどころか、声一つ震えないぼくに向かって、誰もそのように言わなかった。実際のところ、どのように彼らが思っていたのかは知らない。子供の前で気丈に振舞っているように見えたのかもしれないし、あるいは呆然としているように見えたのかもしれない。あるいは、やっぱり何も感じていないように見えたのかもしれない。
我慢をしたわけではない。
泣きまくる上の子を抱きながら何も感じなかったわけでもない。
ただ、直後から歴然とここにある彼女の不在は、ぼくの中の重力を奪い、無法な時間の中にぼくを放り出していた。ぼくは、どの時空にもいなかった彼女と、どの時空にも漂う彼女の気配を追っていた。
彼女は言った。
きっとわたしが死んでも泣いたりしないでしょうね。
よく分からないことで泣いたりしないし、ましてや一人で泣いたりもしないでしょうね。
泣いて欲しいわけじゃない。
ただ、泣きもせず、ずっとおかしな顔でいる方が心配。
わたしは呪いじゃないんだから。
そう言って、彼女は笑った。
パラシュート 追いかけて海 スカートのまま 眩しい波間に 二つのクラゲ
濃い霧に 隠れた風力発電の 音を聴いてる もう少しだけ
四つ葉のクローバー 五つ葉のクローバー ぼくのラッキーガール
おねがいが いっぱいあるんだ ほしいもの いっぱいあるんだ なんでもいいから
もし もしも まるで わたしね うん ぼくが ほんもののきみ うん そうだ
しゃぼん玉 当ててドラゴン倒すやつ 一度も死なず 上まで行けるようになったんだよ
ハッピーセット2つと ビックマックのセットと てりやきのセット
「わたしより 電話を切るのが下手だね」と きみも見ていた 朝を見ている
あとがき
電話を切るのが下手だったぼくたちのことです。
どうせ上手に終わることは出来ない。
あと一つだけ。
ぼくたちのこどもたちは、相も変わらずハッピーセットはナゲットでマスタードに付けて、ぼくはいつものてりやきバーガー、きみのはいつものビックマック。ぼくは、コーラだってきみの分まで飲んで、もう何も飲みたくない。3人しか乗っていない、馬鹿みたいに大きなワンボックスカーを駐車場から南向きのバイパスに出せば、入道雲がフロントガラスの向こうに、カーステレオからはYES, YES, YESと溢れるから、きみたちは窓を開けて、言うんだ、パパはしあわせかいって。ステレオのボリュームを上げていく。窓が閉じていく。ぼくたちの車は舞い上がる。危ないからやめてと、きみが怒っている。こどもたちは小さく遠ざかってゆく街に手を振っている。
後部座席でぐっすり眠る彼らを起こさないように、ぼくはゆっくりと自宅の駐車場に車を入れる。
ルームミラーには、ケータイで誰かと話しているきみの姿。
声は聞こえない。
でも彼女が誰と話しているのか、ぼくは知っている。
ぼくは彼女が履いている真新しいサンダルのことも知っているし。
床に転がっている、サンダルの入っていた箱のことだって知っている。
彼女の口の動きを見ているだけで、その表情を見ているだけで、何を話しているのかぼくにはわかる。
なぜわかるのかぼくは知っている。
不思議なことは何一つない。
あの頃のきみは、あの頃のぼくと話している。
あの頃のぼくはろくでもないことばかり言っているのだろう。甘ったるいことも言っているだろう。途方も無いことも言っているだろう。ほんとうのことを言っているだろう。
きみは呆れたり、退屈したり、笑ったり。たくさんの言葉と言葉を交換して、ぼくたちはぼくたちになった。
ぼくは、いつまでも彼らに話していて欲しい。
この詩集の中で、わたしは一つ嘘を書いている。
もう気付いてる人もいるでしょう。
わたしは詩人ではありません。
(End)