九月三十一日の天気予報 remix
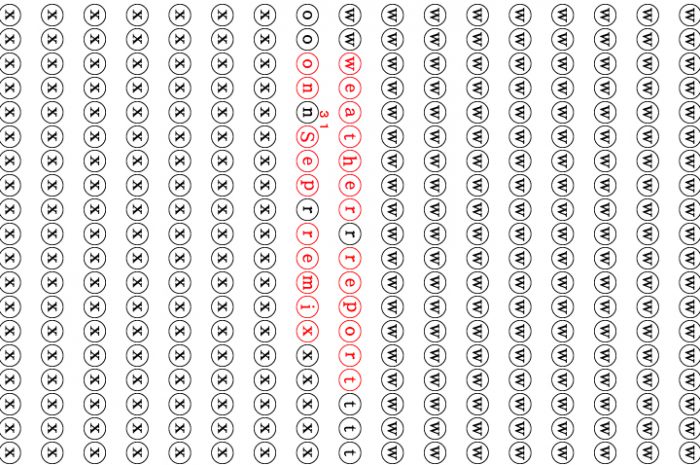
迷子になった飛行機が東の方角へ流れていく。私達は冷たい部屋の中からそれを見送っている。私達の冷たい床と壁の部屋の外には途切れることのない雑踏がある。飛行機、そっちに行っても何もないよ。陸も国も村も果ても。機体に大きく描かれた「我ら、汝らと我らの望んだ侭に」の引用を見ながら、そういうことなら私達も同罪かもしれない、と、ほとんど暗号かおまじないのような言葉を胸の内で返そうにも返せないで、さようならと明日は我が身の自分自身に手を振ることもなく、確かにここにいるのは私達だ。
中音域の和音が長く不規則な休符の間に少しずつ形を変えながら漂う。私は楽譜を読むことは出来ないけれど、この五線譜の無駄遣いにも見える分厚い頁をめくる内に、自分勝手な音楽を再現し始める。どこから来てどこに潜んでいたのかもしれない和音の旋律と、その水平線の向こうから鐘の音色が、残響が、追い込んでいるのか追い込まれているのか分からない静けさを引きずり出して。
矛盾を指摘する者だけが矛盾する。煽る。猛る獣の内なる声に耳を傾けるのは物好きである。細い首に牙を食い入らせながら、対話に挑む者は無力な犠牲である。煽られる。風ではない。波に。波動に。私達は自らを止めることは出来ない。
そのハミングをやめないで。
何読んでるの? お願いだからそっとしておいて。いいじゃん。そんなの置いといてさ、ほら。
そっとしておいてください。雨が止むまで。雨なんか降ってないじゃん。変なやつ。じゃ、一人で海でも見に行ってくるよ。正確には海以外のものも見るんだけれど、と言いながら。
防波堤に立って見下ろす海はいつも緩やかで、まるで僕のものではない誰かの胸を締め付けるようだ。波はこのなだらかなコンクリートと飽くことなくじゃれ合い、一秒後には忘れ去られる言葉を耳元で囁き合いながら、その境界をいつしか曖昧にしているようで、僕はお天道様に内容のない同意を求めるけれど無関心。真昼の直線状になった太陽光は海面を一斉に照射し、その慈愛と毒素に満ちた攻撃はまばらに見える釣り船や、その遙か下方に蠢く魚群の幻すら光の元にあぶり出そうとしているが、海は素知らぬ顔でゆらゆらと透けることのない深色の群青を湛え、まるで僕のものではない誰かの胸を締め付けるようだ。
だめだ。ハミングが聴こえてくるのは、まさか海岸線に並ぶ電信柱の天辺に設置され沈黙を続ける緊急時用のスピーカーからではなく、僕の記憶の甘ったるい部分から。僕は防波堤の上でヘッドホンを耳に涙を流す猿じゃない。どうせ僕の中の緊急時スピーカーは壊れているに違いない。警報色に染まった空にも気が付かない。
ここから飛び降りるのはどうだろうと思った。まだ夏だし、飛び降りたくらいで、でも案外気持ちよく死ぬのかも。音がして無秩序に見せて宇宙的な透明の飛沫が四方に散って、きっと海は眉一つ動かさない。波紋の真上に鳥が来て鳴いたのは偶然だろうか。どこからか神妙な面持ちの人が現れて心の中で何かを言う。そうなのだ。僕は穏やかな海面を眺めながらそう思った。第一僕は泳ぎが得意だ。
「すきだあああああああ」
僕は海に向かって声を放った。声は海面にすら届かず、辺り一面に次々に射し込む光の数え切れない屈折によってバラバラにされエーテルに。缶ジュースを買いに行っていた北里が笑いながら駆け寄ってきた。
「ありがとう。今まで気付いてあげれなくて、ごめんね」
「おまえに言ったんじゃねえ」
「きもおおおおおおおおおおおおおい」
と北里は僕の声の全てが倍の大きさで叫んだ。
彼女は僕にコーラを突き出して渡すとすぐに自分のジュースのプルタブを開けた。手に取ったコーラは水滴でびしょびしょに濡れていた。
「どこまで買いに行ってたの?」
北里はジュースを一気飲みするような勢いで喉を鳴らし、それから満足そうに口元を拭い、隣に広がる水平線に目をやりながら、理論上では太さのないその頼りない線を指で弾きながら言った。
「ね、煙草ちょうだい」
「また?」
僕と同じこの街に住む北里とは四つ? 五つか。前のバイト先で知り合った。定職にも就かずバイト先を流々転々としている僕と同じように偏西風に乗ってふらふらとしている北里が出会ったのはきっと誰かの夢の中だった。あるいはデジャヴ。実際タイミングが一ヶ月でもずれていたら僕たちは出会ってはいなかった。僕がそのバイト先に勤め出してから最初の給料日を迎えるより早く、北里センパイは突然そこを辞めた。あとで理由を訊いてみると彼女は「知りたくもないこと、訊ねたりしないこと」と言った。
「思わせぶりは悪い癖」
「想像力が逞しいのは臆病という名の悪い病気」
缶ジュースを飲み干し、煙草を吸い終えた後もなお、海は翳り一つ見せないまま延々と単調な波に揺れていた。既視感そのもの。そこには国境や歴史や時間の概念など初めから無い。寄せては引く運動には一分の隙も無駄も無い。海風にからまった髪を押さえ北里は僕に二本目の煙草を催促し、僕がその手を握ると、ライターで火を付けられそうになったので、大人しくもう一本渡した。強い風に身をかがめて何度もライターを擦りながら北里は言った。
「死んだらどうなっちゃうのかな」
僕は北里に近付いて手で風よけを作ってやった。それでも僕たちの隙間を悠々とすり抜ける気流に北里は目を細めて言った。
「死後の世界とか」
「グレイト」
「輪廻転生とか」
「ファンタスティッ」
やっと煙草に火がつき、北里は肺いっぱいに煙を吸い、吐いた。北里の鼻の頭には透明な汗が粒のように浮いていて、僕は言った。
「そのうち月のラビッツの正体みたいに、なにかわかるんじゃねえの」
「すごいよね」
「そうだね」
「どっちがいい?」
僕は既に潮風が充満した自分の肺のことを想像した。肺胞に無数に巡らされた色とりどりの毛細血管にはさっき吸ったはずの煙が少しだけ残されていると思った。それが完全に消えてしまうまであと何光年だろうと思った。
北里は何やら挑戦的な瞳で僕を見上げていて、僕は吸い殻を空き缶の中に入れ、それを海へ思い切り投げた。空き缶は小さくなって見えなくなるまで遠く飛んでいった。
「満ちよ、潮!」
「高市くん、もうすぐ干潮なんだけど」
そう言って北里は海岸沿いに転がるテトラポットを指さした。そこには半身が剥き出しにされた肺胞のようなコンクリートの構築物が転がっていて、水からあがったばかりの表皮に艶めかしい海草類が光を浴びて輝いているのが見えた。その意味もなく艶めかしい光沢を眺めていると北里が言った。
「あと、ポイ捨て禁止です」
「どこに書いてんだよ」
「カーマスートラのオールカラー版」
あの鳥、かなり遠くを飛んでいる。なのに、あの大きさ。化け物みたいにでかいんじゃねえの。
聞いてる? 私の話?
「私だってどっちでもいいに決まってる」
「何が?」
「何が?」
北里は空に向かって煙を吐く。知らないうちに遠くの雲が冬布団のように厚ぼったくなっているのが分かる。煙は彼女の唇から離れるとすぐに薙ぐような潮風によって妙な角度にねじ曲げられ、ここから少し離れた僕たちの住む街に届く前に、中空で力無く散り散りに消えた。
僕は空を見上げる北里の視線を追って言った。
「これから降るんだね」
「降りません」
密林の中でもう7日間も足止めを食らっていた。本当なら今頃はボートで川を下り、帰国の途に着いている筈だった。用を足しにテントから少し出ただけでレインコートのどこかから水が染みいってくるような、叩きつけるような雨が止まない。
現地ガイドはこの宿営が始まって二日目からほとんど口を利かなくなっていた。彼は最初、単なるスコールだと言ったが、日が暮れても止まない雨に表情を強ばらせ、嫌な感じがすると言った。
ラジオの電波も拾えないような深い森の中で身動きが取れなくなってしまった。食糧も心細く、ガイドに強引に進んでみてはどうかと言ってみたが、これだけ雨が降ると至るところで道が沼化しているので動かない方が良い。嫌な生物も活発に動いている、と言った。
雨色に満たされた密林の中では激しく地を打つ穏やかな時間に混じって獣の叫ぶ声がしないでもなかった。それが気のせいなのかすぐ近くで起きている現実なのかは全く分からなかった。
学生達は日々憔悴していったが、さすがに教授は慣れたもので、体力を温存するために目を閉じているかと思いきや、急に帰国後のスケジュールについて詳細に打ち合わせを始めたりと、とてもこんなタフな人間にはなれそうもない、と助教授や学生達を改めて打ちのめした。
そして8日目の朝だった。我々は三基のテントに別れてこの悪夢が過ぎるのを待っていた。まだ雨は一向に弱まる気配がない。どことなく夜が明けかけた頃である。一つのテントで女生徒の叫び声が上がり、残る二つのテントの者達は雨の中に飛び出した。
生ぬるいシャワーの下、叫び声の上がったテントの入り口に赤く薄い毛皮のようなものを纏った屈強な人間が立っているのが見えた。胸のふくらみからすると、それは女だった。現地ガイドはその姿を見るなり、全身を震わせ川のようになった地面に伏せた。遅れてテントから出てきた教授は、それを見ると「またか。いや、違う。若すぎる」と言った。
恐縮ですが先生、アマゾネス物ですか、逆に斬新ですかねえ。流行ってはいないですね。いやあ、どうでしょう。B級どころか、ねえ。ドキュメンタリーならまだしもですが。大体、密林の中でずっと雨を降らせるのって、すごく予算がかかるんです。CGですか? その方が高くつきますよ。現地に行けばずっと雨が降ってるんですか? それこそ撮影になんかなりません。お願いしますよ。普通に書いて下さればいいんです。『わすれないで、わすれてよ』みたいな、あれはすごく良かったですよ、ああいう話をお願いできませんかね。すいませんねえ。世界を救うんですか? ブリッジマンが? それはすごいんですけど、すごすぎるというか、予算がそんなにないんですよ。既にスケジュールも喰い始めてますし。いやあ、世界が救われたかなあ、ぐらいでいいんですけどねえ、こちらとしましては。
おい、本当にあの先生、大丈夫か? いくら雨の魔術師って呼ばれてたって言っても、もう二世代も前の話だろ? 今の連中は知らないだろ。名前で客が呼べるわけでもないのに、うちの上の連中は何を考えてるんだろうな。そう言えば、あれだろ、あの先生、この前現地の子供を認知したって言ってたよな。なんだか何が何だか分かんなくなってんじゃねえか。まさか実話を書こうって言うんじゃないだろうな。今回はそういうんじゃねえんだよな。まいったなあ。
北里の父親は気象予報士とかいう職業で、それを聞いた僕はてっきりテレビに出ているアレかと思って「どの局?」なんて質問をしてしまったのだがどうやら違うらしかった。
フライデナイト。
「それはお天気キャスターでしょ。気象予報士って言っても色々あんだよ。私もよく知んないけど。私の父さんがやってるのはすげー地味な仕事でね、スーパーとかコンビニとかの天気別売り上げデータなんかも作ってんの」
「どこで?」
「会社で」
「何の会社?」
「だから、民間の気象会社」
「何それ」
サタデナイト。
有能だというのは凄いことだ。何の能もない僕には想像もつかない世界だ。北里は僕が知る限りこれまで一度も天気予報を外したことが無い。だからどこかに遊びに行く時には僕は必ず北里に電話をかける。すると北里は面倒くさそうに天気を教えてくれる。マイ天気予報、そう言うと北里は近くにあったゴム製のガードレールを蹴って言った。
「ヤなんだよそうゆうの。昔っからイヤ。うちの父親、毎朝ご丁寧に冷蔵庫に今日の天気書いた貼り紙していくんだよ。でっかく『晴れ』とかさ。どうしても目に入っちゃうんだよ」
それは父親なりの家族愛だろうが、北里にとっては迷惑のようだった。便利だと思うけどなあ、と僕が言うと北里は今度は後ろ回し蹴りでガードレールに一撃を加えると、そっちは風雪にやられていたらしく、柔らかに弾かれることなく無惨に砕けた。
「気象予報士の家族以外には分かんないよ。まるでだよ、もしかしたらその日は快晴だったのかもしれないんだよね、でも、父親が『曇り』って書いて貼ったせいで、どこからともなく雲が出てきてさ、というふうに思えてもくるんだよ」
「魔法使いじゃあるまいし」
「というふうに思えてしまうのがイヤ」
北里、それは言いがかりだ。
「どうせなら一日の終わりに言ってくれればいいのにさ」
「それ意味ないじゃん」
「言うと思った」
風がないね。
あるよ。見て。
岬の方に幾つかのパラグライダーが見えたと思うと、岬の陰から幾つも幾つも続いて湧いてきた。好きな人もいるもんだな。燃えるような夕日の中でそれらの透き通ったシルエットは水母のように見えなくもなかった。
北里は目を伏せて口を尖らせ、目を閉じ口を開き、付け加えて言った。
「美夏にも同じこと言われたよ」
どこまでも続くような光の国。
それはこの国のことです。
四方を漆黒の海に囲まれた細長い島は、凍えるような夜にもまばゆい光を放つ。
絵本や映画に登場する悪趣味な理想郷なんかよりも、よっぽど光の国。
上空を旋回しながら、こんな国に不幸が続くことは当然のことのようにも思えたし、こんな国に幸福がないのが不思議な気もした。
隣のシートにかけた褐色の肌をした美形の外国人男性が、夜は暗い方がいい、明るいと眠れない、眠れないと頭がおかしくなってしまう、私はこんな国では眠れる気がしない、とでも言いたそうな表情を浮かべ、目を閉じた。
この光の国のどこかに美夏もいるし、北里もいる。
そう考えながらゆったりとした街の灯の拍動を眺めていると、男性は薄く目を開け、ああいう化け物と生きてきた君達は、もう光の作り出す残像にも、再現される時間にも、現前する幻にも、抗う術を失ってしまった。十分、苦しんでいる。我々の国の言葉で言えば、十分な罰を受けている。と言った。
北里と僕には共通の友人がいた。ハウスキーピングのバイトで知り合い、ライフキーピングと称して三人でよく歌いに行った。美夏というその女の子が僕たちの前からいなくなったのは一年前のことだ。北里との行き場のない口ゲンカやすれ違い、そんなことがあった。美夏ちゃんは僕と北里よりも一つ年下だった。そのせいか僕たちにやけに甘えてくるところがあったし、顔立ちも幼かった。オシャレなのかダサイのかよくわからない服を着て、見たことも聞いたこともない本を読んでいて、過酸化反応が逆行しているかのような活発な女の子だった。
美夏ちゃんのことで強烈に覚えているのは、彼女がノストラダムスの予言を口うるさく言い続けていたことだった。もうとっくに終わってしまったことなのに、あれは実は計算がズレてたの、いえ、わざと間違ったのよとか、キョーフの大王というのは一説には世界的な伝染病で、その病気はまだ報告されていないけど南アメリカの一部の地域では既に謎の大量死が発生してるの、とか、どこで仕入れてきたのか分からないことをあれこれせっせとせっせと周囲に吹聴していた。
ノストラダムス。
「でもね、私はそうゆうのじゃないと思うのー。ホントはね」
「そういうの?」
「うん、そういうの」
美夏ちゃんは僕たちがよく利用していたカラオケスナックの窓際に座って楽しそうに喋る。北里はもう話に飽きていてぼんやりと外を眺めている。僕は適当に相づちを打つ。
「じゃ何なの?」
「隕石カモン」
「♪ハリウッドスキャンダル」
「でも世界の終わりってそうゆう感じがしない?」
「まあね」
「そうなったらいいのに」
「略取と強姦の時代よ、さらば」
「金権と乳児殺しの惑星よ、さらば」
「猥談と説教の祭典はもう終わり」
「嘘つきと格好つけどもの言葉を笑い合え」
「やって来い!」
「何が?」
「やって来い!やって来い!」
美夏ちゃんはいつものように本気か冗談か分からない顔をして本気か冗談か分からないミルクティーを飲む。元々予言どころか予報すら嫌悪している北里はそういった種類の話を嫌がり、段々と不機嫌な顔になってくる。美夏ちゃんはそれに気付かない。
「オーーーーーケーーーーーー!いつでもいーーーーーぞーーーーー!」
美夏ちゃんと連絡がつかなくなってからも僕たちは時々そのカラオケスナックに顔を出した。けれど店は僕や北里の街と美夏ちゃんの街のちょうど真ん中にあったので、そのうち僕たちは地元で別の店を見つけ、いつしかその店に足を運ぶことはなくなった。
北里は綺麗な横顔で僕に言う。
「美夏の言ってたようにさ、もうすぐ隕石が落ちてくるとしたら、今から何する?」
僕は黙って煙草に火をつける。
「私は別に何もしないよ。やりたいこと、やり残したこと、あるかもしれない。でも、私は何もしない。分かるかい? 高市くん」
北里は黙って手を差し出す。僕がその白い手のひらに煙草を一本乗せてやると、北里は笑って僕に言った。
「もう一本」
この店の年代物の通信カラオケ機材は壊れているのか、最初っからそういう仕様なのか、「速く」ボタンも「遅く」ボタンもどこまでも押し続けることが出来る。他に客がいないことをいいことに、僕はどこまでも「速く」ボタンを押し続けたら、音楽はどこかから光になった。
「北里、何歳?」
「てめえと一緒だよ」
「じゃ、三十四か」
「文句ある? 大丈夫? 飲み過ぎてる? まだ午前中だよ」
「やって来い!」
「けどホントにそうなったらさ、隕石も私が予報してあげるよ。人類のために」
もし君達に信じる力が残っていたとしたら、数ある中から、北里の言うことなんかを信じてみることが出来るかい?
「どうせなら世界が終わった後に言ってやればいいじゃん」
「それじゃ意味ないじゃん」
まだ午前中。これはプロローグ。ほとんどプロローグ。
これはエピローグ。まるでエピローグ。
僕は相変わらずアルバイトをして同じような毎日を繰り返し繰り返して過ごしていた。今のバイトもそろそろ辞めようかと考えたこともあったが、何となくそのまま同じ職場で同じ仕事を続けていた。僕はバイトの帰り道、駅から家まで歩いて帰る途中にこの夏の出来事を思い出してみた。いくつかのイベントに顔を出し、バイトに三回遅刻し、バイト仲間の女の子と飲みに行ってヤッてしまって気持ちよくなり、家のステレオが文字通り音もなく壊れた。
海くらい行けば良かったかなあ、と思った。僕たちの街には海があるが、海水浴場は無い。もちろん泳ごうと思えば泳げるのだが、ヒットチャートを彩るような人々はこの街の海で泳ごうなんて考えないようだった。記憶に問題を抱えた人々はもっと南方の海へ行く。幼い頃の記憶を失ってしまったかのように。南方の海は確かにいい。白い砂と星、清潔な飲み物。素晴らしいシャワーの水流。でも。藻屑に足を取られたり、更衣室の隅に落ちた血まみれの水着や、砂まみれで毛のない恥部が露わな幼女などを目にすることもない。でも。自問自答に敗北することの恐怖と常に戦うなんて。
いずれにせよ、そんな季節は過ぎた。転がってきたコカ・コーラの瓶も、もうどこかの草むらの中で光を失った。
ふと僕は思い立って足先を海の方へ向けた。
とっくに日は暮れているのに夜のアスファルトにはまだ膨大な熱が残っていた。無数のヘッドライトがその熱に頬ずりしながら通り過ぎた。彼らは優しく、時速60キロでエアコンをつけて、各々が向かう場所へ、時間と同じ速度で流れていく。生命と同じ速度で進んでいく。
僕はガードレールをまたぎ、その光の束の隙間を横切った。
少林寺拳法の教室帰りらしき子供達が自転車に乗って、互いに突きや蹴りを応酬し合いながら、僕の傍らを過ぎて行った。
住宅地に入り、幾何学的な文様の通りを有機的に歩き、やがてそれを抜けると郊外の太い国道に出る。そのもっと遠くへと吹き込んでゆく生温い風と共に僕は歩いた。
風の流れに潮の匂いが混じるほど海に近付いた時、僕は道路の右手に光り輝く見慣れない悲しげな建物があることに気付いた。それは新しく出来たコンビニだった。
そこから出てきたのが本物の天気予報士、北里の父親その人だった。意外なことにお父さんの方が僕に気付いて会釈してきた。僕はまるで恋人の父親にばったり会ってしまったかのように固くなって下手くそな会釈を返した。
「今日はあいつ一緒じゃないの?」
と、お父さんは言った。他意があるのか、ないのか計りかねる言い方に僕はどぎまぎした。僕には別に何も後ろめたいところもないわけだけれど、北里が清廉潔白な嫁入り前の少女でないことを知っている僕なんかは共犯に違いなく、まいったな、こりゃ。
「今日は、一緒じゃないです」
「あっそう」
と、お父さんは言った。北里の話を聞いているから知っている。あまり固いことを言うお父さんではないのだ。仕事と天気図が恋人で我が子なのよ、あの人。とは言え、やっぱ緊張する。
なんにも話すことなんかない。
そう言えば、いつだったか。北里の部屋に行った時だ。どういうわけだか、僕が北里のベッドで寝てて、そこにこのお父さんが入ってきたことがあったな。北里はパソコンに向かってメールか何か書いてて、僕が布団の中に入ってて。そういう時って身動きとれないんだよ。飛び起きて土下座するのもおかしいんだけど、布団に横になったまま、あ、おじゃましてます、なんて、マヌケだ。リビングのリモコン、また持って行っただろ。あ、ごめん。なんていう父娘の会話をいい年こいて横になったまま聞いている僕は一生マヌケだ。
ウェイブ。
覚えてるかな。覚えてるだろうな。嫌だな。コンドームなんか手渡されたら。
いいです、そんな、お父さん、そんなに、いいです、一つでいいです、一番安いのでいいです。
違うんです。北里とはそういうんじゃないんです。オジサンには分からないのかもしれないけれど。でも、大人って時にほんとに分かってるんですよね。
「タカイチくん、だよね」
「はい。高市です」
「海に行くの?」
「え、あ、まあ」
「乗って行きなさいよ」
突然そんな提案をされて僕は戸惑った。まさかそんな展開になると思わなかった僕が黙っているとお父さんは有無を言わさずエンジンをかけた。なんてヤニ臭い車だろうか。カーステレオからは、ときめきトゥナイトのオープニングテーマが流れていて、マジか、と思った。
「これ? 間違って買ったんだけどさ、いいだろ?」
若い恋人でもいるんじゃないのか、って選曲でもないし、北里、オマエのお父さんイケてるよ。
「お父さん、エンディングテーマの方も知ってますか?」
「女の子~は 恋をした時か~ら 超一流のマジシャンに早変わり~」
それじゃ演歌みたいだけど、いい! FuFuFu~。とか言いながら僕たちは海岸線を飛ばして、エンドレス~、深呼吸~、いずれこのお父さんも荼毘に付され、北里を守るものが一つこの世から失われる。ハンドルを握るこの手がこの世から失われるということの、底の見えない怖さが僕の横に座っていた。自分の親に対しては感じないくせに、北里が父親を失う日のことを想像して、僕は真顔になり脱力してしまった。冷蔵庫にはお父さんの最後の天気予報がいつまでも残り、その日から北里は天気予報を悉く外しまくるけれど、北里の結婚式の日、澄みきった空の下で、きっとお父さんが今日の日を晴れにしてくれたんだと思いますって涙ながらに言って、その横でハンカチを手渡したりするのは、おい、僕じゃないだろって、北里、その時一体何歳なんだよ。お父さん、僕たちは本当にそういうんじゃないんです。安心しなさい、私達の一族は君達みたいにさっさと死んだりしない。そういうこと? 蘭世の父親の顔ははっきり思い出せないけれど、なんとなく似ている気がしてきます。自分を信じなさい、真壁くん。高市ですけど。めちゃくちゃだ。北里も蘭世と全然違うだろ?
あまりにヤニ臭いから僕は窓を開けさせてもらった。気持ちいい。子供に戻ったみたいだ。
こんなの、きっとあとで北里に言ったら「何ソレ」と大笑いするだろうな、と思った。
防波堤が入り江にそってカーブする底のようなところで、車は止まり、ヘッドライトが消えた。車から下りるとお父さんは胸ポケットから煙草を出して火をつけた。風はこの闇の中を音もなく飛び交い、そのせいでお父さんの煙草にちゃんと火がつくまでしばらくかかった。お父さんは防波堤に腰を下ろし、暗い油のような海を眺めて言った。
「あいつ、まだ煙草吸ってるんだろう」
ごめん、北里。
「どうしたもんかな」
目が慣れていないせいか、海を知覚できなかった。自分が目を閉じているのか開いているのか分からなくなる。風とともに身を揺らせて緩慢にうねり続けるそれは泥のようでもあったし空のようでもあった。気まぐれな風はその表皮をかすめるようにしてすくい取り、その匂いを僕たちの鼻先へと近付ける。むっとするような夏の匂いだ。世界から深く沈み込んだ場所には熱が一際強く残されている。
「男だろうが、女だろうが、古い人間だろうが、新しい人間だろうが、とは思うんだけどね」
そう言って義父さんは防波堤をぺたぺたと叩いた。(だから、義父さんじゃねえって)
北里のお父さんは僕の方を見て言った。
「こいつも随分と古いんだよ。なんせ、俺が生まれた時からここにあった」
「ということはだ、あれも知ってるわけだよ」
「あれだよ」
「それだよ」
「俺達が知らないあれだよ」
「こんなコンクリートなんか、かわいいもんだよ。柔らかいもんだよ」
「小さいもんだよ」
僕は何の相槌も打たない。でもお父さんは一人で喋り、そして言った。
「戦争だよ」
俺達は首から名札を提げてな、そんでもって、経歴と罪状と年齢でアドリブで言い訳して、わずかな晴れ間に夜にして、無数のサーチライトを空に向けて、愛する者を守るため、とか言うんだ。誰がそのことを否定できる? 誰が肯定できる? 誰が話せる? 誰が笑える? 拍手を贈れる? お前だよ。お前達だよ。抱き合って、目を背け合って、殴り合って、隠し合って、ヘイヘイヘイ、慰められて、雨でも飛ぶしかないんだ、思ってることと全然違うことが口をつくのは、誰のせい?
明日の朝のパンを買いに行こう。とかね。
分かってる。
そこにいるやつが一番偉いんだぞ。
お前の横にいる人が一番偉いんだぞ。
なんて強いガッツポーズなんだろうか、と僕はお父さんの後ろ姿を観ながら思った。
お父さんが先に帰ったあとも僕はしばらく防波堤に座っていた。充分に日中の熱を含んだ風たちが見下ろす闇へと次々に姿を消していった。
お父さんの持っている意志のようなものは自分には無いと思った。僕はこの闇の中に吸い込まれる自分を想像した。音もなく沈んでゆく星は、この恐ろしく深い闇はどこに繋がっているのだろうと考えた。
帰り道、行く手からまとわりつくような逆風が吹き続けていた。
お父さんは言うだろう。放射冷却された空気は、山の斜面を下り、海へと雪崩ていく。
夢の中で、しばらく寝ようと思った。寝言で「もうおしまいだ」と言った。たった今、正義の剣によって王を失った城が音を立てて崩れていく時のように、偉大だった王の側近のように、僕は「もうおしまいだ」と言った。もう寝よう。しばらく寝よう。
北里が、うなされる僕を起こした。
「お父さんの夢を見たよ」
「苦しそうだった」
「僕は宇宙船なんかじゃない」
「そう思うんなら、はっきりそう言えばいいじゃない」
「北里は吸血鬼なのか?」
「私は吸血鬼なんかじゃない」
「吸血鬼はみんなそう言う」
「言わないわよ」
北里はバイトをやめてミュージシャンを目指し始めた。どこで知り合ったのはよく分からない連中とバンドを組んだのだと言っていた。あまり才能に溢れた感じの人達じゃないのよ、と北里は言った。その方がいいでしょ? だって、才能ってそういうものでしょ? 知らないよ。自分で考えろよ。
それから頻繁に僕の家に出入りするようになった。
「ヒマなんでしょ」
「悪い?」
「どうせなら献血とかボランティアとかすれば?」
「献血してきたわよ」
元々あらゆることに興味が薄かった北里だったが、僕の部屋に来るようになってからその傾向は以前よりも酷くなっていた。ギターの練習をする北里のチューニングはいつも狂ったように狂っていた。気付いてる? 北里はギターを抱いたままソファーに横になってぼんやりと天井を見上げる、そんな日が何日か続いた。
ある夜、僕がバイト先の送別会兼カラオケ大会から帰ってくるとアパートの入り口で北里が待っていた。手には聞いたこともないスーパーのビニール袋がぶら下がっていて、訊くと晩飯を作ってくれると言う。珍しいこともあるものだ、と僕が喜んだのも束の間、北里は部屋に入るなり「疲れた」と言ってベッドに寝転がり、僕がネットで今日のプロ野球の結果を確認しているうちに眠ってしまった。
ビニール袋を漁ると中には豚肉と紫蘇の葉が入っていて、そう言えばこいつ料理出来たんだっけ、と改めて思った。確かにずっと実家だし、毎朝格言が貼られているような家だからきっと家事一般などをムリヤリ教えられたのだろう。僕はベッドでだらしなく寝息を立てている北里を見て、まさか親も娘がこんな風に育つなんて考えてなかっただろうなと思った。
豚肉と紫蘇のポトフ風。
煮上がった頃、タイミングよく起きた北里は「何これ」と言った。
「怒んなよ。お前が寝るから悪いんだよ」
「メリークリスマス」
「まだ九月だよ」
「食べていい?」
「食うの?」
美味いも不味いもなかった。食事中にふと北里を見ると彼女が妙な笑みを浮かべている。名シーンみたいだった。その顔がなんだか嬉しそうに見えたので僕は訊いた。
「美味い?」
「美味いわけないじゃん」
食後、北里は僕の淹れたコーヒーも飲まずに、ヘッドホンをしてギターの練習をし続けた。
「コーヒー、ぬるくなるよ」
と僕は言ったが、どんな音量で練習してるのか、北里は全く聞こえていないようだった。
「今時バンドなんて流行らないぜ」
「北里」
「あ、ニュース速報」
「あ、地震速報」
「デブ女」
「肉まん」
「やりまん」
「なあ、北里、結婚しようか。もう、三十四だし」
「邪魔しないで」
最終のスポーツニュースも終わったので、僕はコーヒーを淹れ直した。北里は練習をやめた。テレビを見ながら、眠たい、と北里は言った。
ピースフルピース。
「防波堤?」
「うん。波が越えちゃうかも知れないって。父さんが言ってた」
「言ってたね」
「今台風来てるでしょ」
「オタクじゃないから知らない」
「でっかいの来るんだよ」
チャンネルを変えると、スタイルの悪い水着アイドル達が今回の台風について深刻そうに話していた。彼女達によると、台風9号は予想では三日後の夜に日本列島に差しかかるとのことだった。
「防波堤越えるのかな?」
僕がそう言うと北里は煙を吐きながら言った。
「でも父さんは方向が逸れるって言ってるけどね。今回は」
衛星による地球の姿が映し出されていた。北里と僕はその画面をぼんやりと眺めていた。画面では予想された雲の動きが緩やかに描かれていく。その動きには少なくとも悪ふざけは無いと思った。雲は動くべき方角へクールに移動しているように思えた。だいたい地球が生まれてから雲や風や太陽はそうして活動を繰り返しているのだ。人間が誕生するより遙か太古の時代から、何千年、何万年とそうしてやってきたのだ。人々の願いを乗せた気象衛星が傷だらけになりながら宇宙を飛び回り、すべての現象を、あらゆる可能性を管理したところで。
煙草の灰が落ちかかっているのも知らず、北里は地球とグラビアアイドルをずっと眺め続けていた。
カラオケスナックで僕と北里が歌いまくってる間にも地球は回っていて、二日後、お父さんの予報は外れてしまった。テレビは急速に勢いを増した台風9号が早ければ今日の夜半に上陸すると伝えていた。僕はテレビのスイッチを切ってカーテンを開け、すると遠くの厚い雲が強風に流されているのが見えた。飛行機はどこにも見あたらない。ここから見渡せる風景はすべて光が遮断されたあとの灰色の世界で、その中でただ風だけが自覚なく中空を飛び交っていた。風は人々のように気が触れていて、けれど何故か奇妙なほど静かで、眼下の街並みはこれから来る何かにひっそりと備えているかのように皆押し黙っていた。
時間が経過するにつれ、風の量は明らかに増大していった。それはもはや一定の方向へ吹く季節風や海風ではなく、群衆のように意味ありげだった。闇が少しずつ窓の外を覆い始め、やがて小さな雨音が聞こえてきた。暗転する部屋の中で僕は単調なテレビニュースを眺めていた。遠い国の革命、訃報、最新の科学技術、子供達のチャリティーバザー、政治家に憤る街の声、サバンナの夜明け、大正琴、DJ、プロレスラー、無職、喋るエビ、そんなものに混じって雲の様子が時々放映された。大陸に近付きすぎた台風は本腰を入れた気象衛星によってこれから取り得るすべての行動を完全に掌握されていた。挑発に乗るかのように、目隠しをされているかのように、人質をとられているかのように黙々と進む台風の下、描かれる等圧線は一糸乱れぬ包囲網を張り巡らせている。テレビを消そうとした時、不意に携帯電話が鳴った。北里からだった。
「どうした?」
「今から行くよ」
「さすがにどこも休みなんじゃない?」
「ばか。スナックじゃないわよ。防波堤よ」
それだけ言うと北里は電話を切ってしまった。何かの冗談かと思ったがそうではなかった。北里は僕と違って冗談を言わない。窓の外を見ると雨風は次のステップに差し掛かったようだった。大粒の水滴が窓ガラスを叩くばりばりという音が耳に届く。マジかー、と僕は呟き、もう一度有名なコメディアンの物真似で「まじかぁ」と言い直し、選択の余地も無くすぐに傘を持って玄関を飛び出した。
どちらから襲ってくるか分からない急な暴風に何度か転倒しそうになりながら僕は自転車を海へと走らせた。住宅地では大多数の家が雨戸を閉め切りじっと身を固くしている。人類の最高の叡智である傘が役にたたない。
車の消えた国道を横切り、ようやく辿り着いた海はまるで別物に変貌していた。明らかに水位が上昇し、見慣れたテトラポットも、眼下に転がる岩々もとうの昔に姿を消してしまっていた。海は大きく緩慢に揺らぎ、それは腹を空かせた巨大な生き物のようだった。干潮も満潮も関係が無かった。ただ海は溢れる自己を抑えられないように虚ろな瞳で暗い巨躯を揺さぶっていた。
防波堤の上に北里の姿が見えた。僕は自転車を降りて駆け寄った。北里は傘も差さずに古いコンクリートの上に座り込んでいた。
「何してんだよ」
北里の重く濡れた髪の先から雫がとめどなく落ちていた。時折激しい気流が起こり僕たちは風とも雨ともつかない混乱の中に巻き込まれた。北里は風の中、大きな声で言った。
「見たいんだよ」
「何を?」
北里の瞳は何か強い光を湛えていた。それは北里がこれまで僕に見せたことのない意志の光だった。不意をついたその目に気圧され、僕は諦めて言った。
「取りあえず階段のところまで戻ろうよ」
僕は北里を立たせると防波堤に掘られたコンクリートの階段まで連れていった。段の途中で海を背にして腰を下ろす。背後の海からは咆哮のような海鳴りが聞こえていた。南から来た仲間に煽られて闇が活性化しているのだと思った。
北里は僕に手を出した。
「たぶん湿ってるよ」
ポケットから煙草を取り出して北里に渡すと、彼女は自分のライターで懸命に火をつけようとした。この暴風の中では火がつくとも思えなかったが、やがて成功したのか、北里は魔法の煙を吐いた。僕は魔法の意味なんて知らない。魔法なんて見たこともないのだから。でも北里の吐いた煙は、暴風の中なのに、どこにも飛ばされず、北里の目の前で止まっていた。嵐の中で震えて逃げ出せない小さな生き物のように。感情のように。
「お前さ、いつもライターだけは持ってるんだよな」
「高市くん」
「何?」
「最後まで付き合ってくれる?」
一瞬で強烈な風が吹き、小さな煙は巻き込まれるようにして空へ飛ばされた。煙は空中でめちゃくちゃな軌跡を描き、やがて灰色の世界のどこかへ消えてしまった。僕たちはそれをただ見上げていた。
恐怖心は無かった。それはまだ僕たちの目の前には存在していなかった。背後で乱気流が発生しようと、波が無表情に大口を開こうと、僕たちはこの古びた防波堤のこちら側にいて、それは決して覆されることはなかった。北里は黙って身をかがめ、時々重くまとわりつく髪を払って振り向き、海の様子を窺っていた。
周囲から一段高くなったこの階段からは真新しいコンビニのネオンが見えた。そのあどけない輝きを眺めながら僕は親父さんの言ったことを思い出していた。もし仮に、高波がこの防波堤を越えることがあれば、その濁流は一気にコンビニの辺りまで押し寄せるだろう。膨張した海は風と共に僕たちの街へと雪崩れ込み、様々なものをがらんどうの闇の中に取り込もうとするだろう。建物が流され、信号が破壊され、街の機能は失われる。しかしそれは僕の想像の範疇でしか無かった。海は未だ海で、僕たちは僕たちだった。
でもさ。
初めに気付いたのは北里だった。暗闇と雨風で遮られた視界のなか、北里が指さした方角に目を凝らすと、そこには溢れ返った海流が防波堤の先端を濡らせているのが見えた。とっさに自分たちの背後を確認すると、いつの間にか上昇した水位がもうすぐそこまで近付いているのが分かった。来たと僕は思った。これを越える高波が来れば確実にこの防波堤は飲まれてしまう。そう思った刹那、心臓の奥が締め付けられるように収縮した。
「北里」
僕は隣で海面を覗き込む北里を呼んだ。北里も同じ恐怖を味わっているのか、見たことも無いような硬い表情で僕を見返していた。
「ヤバいよ」
僕がそう言うと北里は言った。
「ヤバいね」
僕たちは階段に這いつくばり、顔だけを出して海の様子を窺った。雨に叩かれながら身体を硬直させていると、そのうち何故かこれまでのいろんな出来事が脳裏をよぎった。
「北里」
「何?」
「今、走馬燈見たんだけど」
「んじゃ、高市くんだけ死んじゃうんだね。私まだだから」
「おい」
「ごめんね」
「なんで北里が謝るんだよ」
「高市くんになんか謝ったわけじゃないよ」
「じゃあいい」
そう僕が言いかけた瞬間、僕たちの顔面に強い飛沫が浴びせられた。一瞬視界が白くなり、我に返るとそれが風雨ではなく波の飛沫だということに気付いた。塩の味がしない海。もうそろそろ手が届くのだ。僕は北里を見て、そして言葉を飲み込んだ。
北里は僕をじっと見ていた。
そんな顔すんなよ、北里。
さよなら、北里。
いずれにせよ、さよならだ、北里。
海が届く。
北里はまつげに水滴を垂らせながらまばたきもしない。僕は北里を抱くような気持ちで、身体を合わせているような気持ちで、同じ方角を凝視していた。泡立つ波の飛沫を顔面に受けながら、僕は北里の耳元に口を近付けて言った。ずぶ濡れで冷たく、冷たさの中にぬくもりが残る北里の体を僕は抱き寄せていた。
「1時間後の予報は?」
すると北里は笑い、僕の頬の雨を舐めた。
ムーン。
目を覚まし、枕元の時計を見るともう昼時をずいぶん回っていた。カーテンを開けると厚い雲の切れ端が所在なく浮かんでいるのが見えた。頭がひどく痛んだので、ベッドを降り、台所の棚に置いてあった風邪薬を取り出して、以前北里が置いて行ったウコンの力で流し込んだ。
結局、波は防波堤を越えなかった。あの時間帯をピークに、嵐はやがて徐々に沈静化していったのだった。
気付いたら、また眠っていた。
夢を見た気がした。いい夢だった気がするものの、思い出せなかった。不思議な余韻が胸に残っている。強い余韻。自分の内側と外側が入れ替わってしまったような感覚。枕元の携帯に北里からのメールが届いている。事後報告かと思って読んでみたが、まるで昨夜のことなど何事もなかったかのような内容がそこには記されていた。
ポスト見てみなよ。美夏から手紙。
僕はまだガンガンする頭で玄関に行き、郵便受けを開けた。そこにはビラやDMに混じってひときわ華やかな封書が一枚入っていた。南国の島で屈強そうな現地人と結婚したという美夏の満面の笑みの写真は、ひどい風邪の予感を抱えた人間の脳には、悪い油で揚げた高い肉のように乱暴で、僕は力無く笑った。
この手紙が着く頃には、私がここでダーリンと見送ったサイクロンが二人の街を襲っていることと思います。私にはそれを止めることは出来ませんでした。二人が住んでいる国は、みんなも知ってる通り、みんなが住み始めるよりずっと前からサイクロンの通り道にある国なのです。
でもなぜか、あの国は悪い国ではありませんでした。私もそこに住んでいたから分かるつもりです。
もう何度もめちゃくちゃにされてめちゃくちゃなことをめちゃくちゃな人達がめちゃくちゃなやり方でめちゃくちゃにしてきたのに、でも、思い出しても泣けてくるくらい、あのスナックで歌っていた頃、私は泣かなくても済むくらい幸せでした。めちゃくちゃだけど、ばらばらだけど、人々は信じていたし、祈っていました。
私が暮らすこの小さな島には静かで深い信仰があります。二人には信じてもらえないようなことが毎日起きています。でも、私は思うんです。その国も、負けず劣らず、信じているし、祈っていたんだなあ、と。まったく無自覚に、まったく忘れながら、まったく美しく、信じているし、祈っているんだなあ、と。やりかたがめちゃくちゃで、言葉がめちゃくちゃで、嘘ばっかりついて、忙しくて、でも、どいつもこいつも、信じて祈りながら、ああいう島を作って壊して作り直してきたんじゃないかな。
どうする? 高市さん。北里さんと、その国で暮らしていきますか?
私は大賛成です。私達の子供達がいつの日か、戦場で出会うことになるとしても、私達はいいことの方を考えるべきではないでしょうか。
私は大きな声で言ってるよ。
いいことの方を考えるべきじゃないですか?
手紙には、例のラブラブの写真と、それとどこかで見覚えのある下手くそな絵が付けられていた。
これってもしかして。
髭剃り落とした顔も、案外悪くないよ。ノストラダムスさん。
(End)