ブリザード
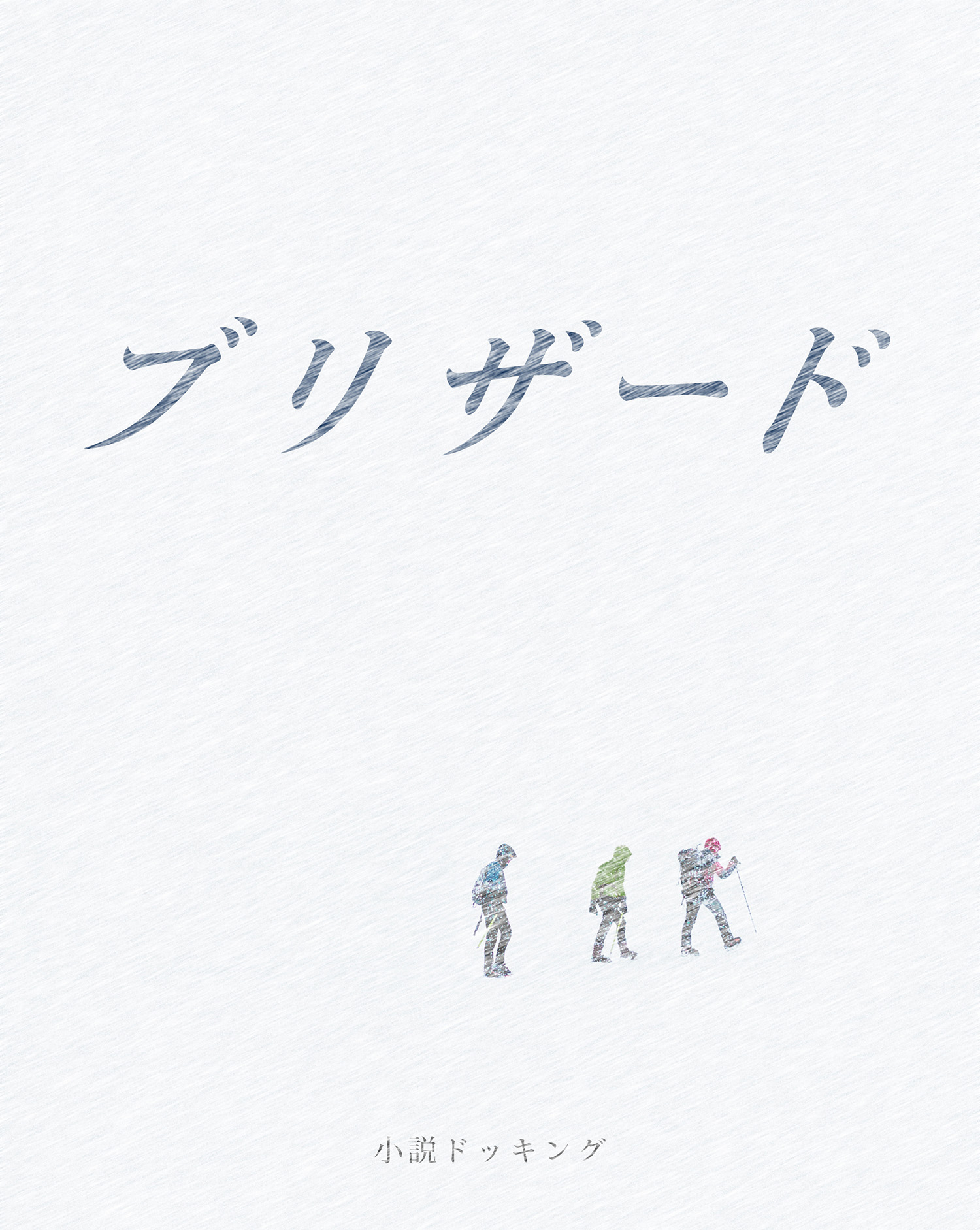
一匹の尾の長い猿が草原を駆け抜けていく。遥か遠くに接近する気配を捉えている。
猿の手足には小石が食い込む。霞む青き稜線。
ネオン。サイレン。色とりどりの旗。濃い口紅。石畳。路地の向こうから聞こえる祈りの声。溢れ続けるコップの水。
駆ける尾長猿の体毛は薄い紫色をしている。隠れる場所などない。
雲は無関心。雨季はまだまだ先。
給水所もない。
衛星もない。
逃げているのではない。やがてそれが捉えることを尾長猿は知っている。
少しでも遠くで牙を剥く。
そういうものである。
朝一番の熱いシャワーを身体に浴びながら、十村は髪のブリーチ剤を乱暴に洗い流していた。髪を茶色にするためではなく、その後に色を入れるための下準備だ。
ダブルカラー。
行きつけの飲み屋でちょっといい仲になった美容師見習いのサツキちゃんが教えてくれた。髪のカラーリングは、まず脱色して、それから色を入れるんですよ。
そうなんだ。
そうなんです。
うん。
ダブルカラーっていうんです。
できるの?
できます。まだ練習中ですけど。
練習する? 俺、失敗してもいいから。
え、どこでやるんですか?
うちのお風呂場で。
えーっ。
汚れても気にしないから。
えーっ。
熱い湯と混ざり合ったブリーチ剤が目に入り、ひどく痛む。そう、この涙は痛みのせいだ。女に気持ち悪がられたくらいで動じる年齢ではない。しかしそれは裏を返せば、女に気持ち悪がられるような年齢になったということか。
まさか、そんなはずはない。
十村の二十代は終わりを告げようとしていた。そしてそれより一歩早く、先月の末に、会社から終わりを告げられていた。ブリーチ剤をすべて洗い流し、タオルで水気を取ると、十村は別のボトルに手を伸ばした。
商品名『スピーディーメイクアップヘアカラー オレンジ』。
根元まで明るくオレンジカラー。あなたも今日から生まれ変わった気分!
キャップを開けると独特の刺激臭が鼻をついた。まさか、髪の色を変えたところで生まれ変われるとは思っていない。自由を得られるとも思っていないし、このクソみたいな8年間のサラリーマン生活で染みついた奴隷根性がさっぱり消え去るとも思ってない。
自分でも、何のためにこんなことをしているか分からないのだ。
根元までしっかりオレンジカラーになるよう、十村は薬剤を丁寧に頭に塗り込んでいった。曇った鏡にシャワーをかけると、そこにはまだ何者にもなっていない、ぼんやりとした白っぽい自分の顔が映っていた。
草原。薄い緑と白の細い線が幾重にも重なり合い混じり合いして揺れている。それが彼方の灰色の山岳の足元まで茫漠と続いているのだった。何一つ遮るもの無く過ぎていく風はいつも強い。
草原に道という道は無い。古より様々な民族がここを抜けて国から国へと渡った。勇ましき者達がおり、追われる者達がおり、商いに勤しむ者達もいた。彼らは皆、ところどころで草の上に頭を出す岩の形や微かな草の色の変化を頼りに目的地へと向かい、地平線の向こうへと消えて行った。数万という軍勢もいた。家畜を引いて移動する一族もいた。中には、この広大な緑色の毛布の上に一人でやってくる者もいた。多くそのような者はほとんど立ち止まることなく強い足取りで進み、なぜか一度だけ立ち止まるものの、また歩き出していくのだった。およそ一度は立ち止まってはみたものの、立ち止まったところで何にもならないことを確認するだけなのだろう。
もしもあらゆるものに意味や理由というものがあるのだとすれば、この一ヶ月もの間歩き通さなければ抜けられぬ一帯の草原の、平らな土や気の遠くなるように退屈な草の群生、単調に吹き抜けていくばかりの風や、草の根元に干からびた無数の小動物の骨、こういったものにどのような意味があるというのだ。積もり吹き去った悠久の時間はあまりにも長く、これから先ここに何万トンもの爆薬が降り注ごうとも、ここが草原であることは微塵も揺るぐことがないように思えてならない。
雲の流れるのは速く、いつも新しい大小の雲が生まれきては去るが、どれも似ている。
一頭の獣が立っている。体躯は馬よりも一回りは大きく、毛足の長いその動物は、膝頭を撫でる草を煩わしがるでもなくされるがままにしていた。人間が住み着くよりも以前より、その獣はこの淋しい土地を住処とし、緑と白の線を食べ続けてそこに身を横たえてきた。草と脚の境目は無いのかもしれない。
獣は一点を見ていた。その方角に何があるようにも思えなかった。どの向きとも変わらない、退屈で代わり映えしない風景。そして彼方に横たわる眠くなるような岩山の稜線。草のゆらぎと稜線のゆらぎ。
微動だにしない漆黒の瞳に映っている空と雲と草原は揺れ流れている。獣が感じていた異変にも、草原は無関心である。
一匹の青いトカゲが、獣の背後の岩の上に登った。それでも獣は剥製のように動かなかった。もっと大きな異変を獣は感じとっていたのだ。
そこまで話して、その見知らぬじじいは「あ、雪」と言った。
振り返ると、並んだボトルの間に覗く窓の外にはいつもの夜で、しばらくそこに雪を待ってみたけれど、ただ黒いままで、だって今は7月の終わりだもん、雪なんか降るわけないじゃん、と思ったけれど、あとの祭、祭のあと? じじいの座っていたカウンターの席はもぬけの空で、おまけにじじいはせっかく作ってやったギムレットを半分以上残していきやがった。
一人残された店内で、じじいの残していったギムレットに口をつけて飲んでいると、どうしようもない気分になってきた。
冬の朝、ベッドを出て行った父はカーテンを開け、まだ布団にくるまっている私達に「うわあ、すごい雪だ!」などと言った。私達は何度もそれに騙され、その度に本気で文句を言った。父も母も「あれ? 雪だるまが溶けてる」とか「あまり積もってないわね」とか色々と手の込んだ騙し方をしてきたけれど、その内、私達は騙されなくなり、父も母も雪のことを言うのはやめてしまった。
本当にカーテンの向こうに雪が積もったことがあったから、私達は騙されたわけではない。
そんなことは一度もなかった。
でも私達は、カーテンを開けたらそこに雪が積もっている冬の朝というものがあるということを知っていて、それを信じていたから、何度もがばっと布団を飛び出していったのだ。
ボトルの間に見えるのは、蒸せかえすような夜だ。
そこの扉を開けて、ビールが飲みたくて仕方のない連中が入ってきたらいいのに。そして、そいつらは武勇伝だの、恋愛相談だの、愚痴だの説教だの、代わり映えのしない話を聞かせてくれる。うんざりしてくる。
じじいの草原の話は退屈すぎて、何が言いたいのかさっぱり分からなかった。
けれど、何が言いたいのか分かりきった話を長々と聞かされるよりはよっぽどマシだと思った。
でも、無銭飲食は勘弁して欲しい、うちも防犯カメラ付けよっかな、でもそこからじじいを探すなんて面倒だし、あ、そうだ、前払いにしよう。わたしは素晴らしいことを思いついた気がしてギムレットを飲み干し、グラスを下げカウンターを拭く。
その時、じじいの座っていた椅子の背もたれに忘れ物を見つけた。
おい。杖、忘れるって何だよ。嘘だらけだな、じじい。
第一章 そして伝説へ
オレンジ色の髪は案外悪くなかった。自分の薄い顔、特徴のない顔に少しでも個性が宿ったような気がした。しかし、まだ何かが足りない。十村は近所の薬局に行き、ジェル(商品名『ハードに決めろ! スーパーハードジェル500』)を購入し、目が隠れる程度に伸びていた髪を逆立たせてみた。
鏡を見ると、もう昨日までの自分はそこにはいなかった。映っているのはオレンジのツンツン頭をした、何かしらの強い意志を持った一人の青年だった。
十村は日暮れを待って行きつけの飲み屋に行き、サツキちゃんの姿を探した。まだ夜になりきれていない薄暗い店内。この時間帯は客の姿もまばらで、サツキちゃんがそこにいないことはすぐに分かった。
待とうか。いや。また出直そう。
挨拶がわりの一杯を飲み干すと、十村は飲み屋の大将に「お勘定」と声をかけた。大将は十村の頭を指さし、似合ってるねぇ、と世辞を言った。
「お兄さん、今日はえらい早いお帰りで」
「ちょっとね」
「サツキちゃんだろ」
さすが大将、と十村は苦笑いした。十村が財布から小銭を出そうとしていると、大将が小声で言った。
「あの子、しばらく来ないよ」
十村は大将の顔を見た。大将は少し困惑したような顔になり、俺もよく分かんねえんだけどさ、伝言を頼まれてんだよ、と言った。
「伝言?」
「あなたが探してる人は私じゃないと思う、だってさ」
帰り道、十村は自問自答していた。自分は誰かを探しているのだろうか。そういうことってあったっけ? 昔から、手先が器用で、なんでもできて褒められる子供だった。友達がうまくできないのを助けてやったり、教えてやったりした。先生には「十村くんを見て、十村くんのようにやってみましょう」と手本にされるようなタイプだった。
就職してからも、誰かに頼ることは一度もなかった。実際、何かができなくて困るといったことが人よりもはるかに少なかったからだ。就職して三年目、パワハラで有名な先輩から「お前にだけは怒りようがないわ」と言われた時、自分には何も欠けているところがないのだと悟った。
しかし不思議なことに、そのことは仕事の評価に繋がることもなく、充実した人間関係の構築にも繋がらなかった。自分にはあらゆる能力が備わっていると思って生きていたが、本当は何一つ手にしていないのではないか。何一つ、手に入れられないんじゃないか。
どれくらい歩いたのか、気付けば薄暮のアスファルトが妙に歪んで見えていた。たったビール一杯でそこまで酔うはずもない。なんだこれ。脳のアレか。そういえば、脳的なアレで死んだやつが同期にいたっけな。
そう思った直後、地面の感覚が消失し、気付けば頬のすぐ側に熱っぽいアスファルトがあった。口の中に血の味が広がった。血の味は久しぶりだと思った。そこから気を失う数秒間、十村はどこかでオーケストラの壮大なファンファーレを聴いた。
アルバイトで雇っている女の子たちが揃いも揃って休暇。常連のほとんどは、そうと分かるとドアから顔を覗かせても「また来るわ」と言い残して、他の店に飲みに行ってしまった。
それでも居座って飲んでいたのは、文房具屋のおやじと工務店の若倅、そしてぶらりとやって来た万々赤だけだった。
文房具屋と工務店は、それぞれ妻帯者で、工務店の方は子どもに恵まれなかったが、文房具屋には子どもが五人もいた。二人とも、わたし目当てで通ってくれている数少ない常連客だ。お互い牽制しているのだろう、鉢合わせた時などは、どちらが先に帰るでもなく、大体閉店まで居座って帰って行く。今夜は長くなりそうだった。
万々赤がカラオケをバックにトランペットを吹いている。文房具屋と工務店は真っ直ぐステージの方を向いて座り、黙って行儀良く聴き入っている。長いリフレインを残して一曲が終わるとささやかな拍手をした。
「やっぱいいな」
「いいわ。いい」
カウンターの上でトランペットを片付ける万々赤に二人はそれぞれ千円ずつ手渡した。慣れた調子で万々赤は会釈をして、受け取った札をポケットに入れた。
「やっぱ楽器とかできるとモテるんだろ?」
「いや、まぁ」
「人によるだろ。おやじがラッパ吹いてもダメなもんはダメじゃん」
「いくらかマシだよ。なぁ、ママ」
「わたしはモテない人の方がいいけどな」
「そりゃそうなんだけどさ」
「逆に楽器やってる女の子って魅力的だったりする?」
「どうかな。吹奏楽部とか? うーん、どうかな」
「お前さ、放課後の教室で笛とか舐めそうだよな」
「おやじは笛を尻に突っ込んでそう」
「お前の発想が怖いわ」
「怖い」
そんな酔っ払いたちの平和なやり取りを万々赤は笑みを浮かべて聞いている。
万々赤はこの辺りの流しのトランペッターで、ラウンジやスナック、こういうガールズバーなどを回っている。トランペットというのは不思議な楽器で、他にもギターやアコーディオンといった流しもやってくるが、万々赤がトランペットを吹くと、男達も女達も皆その表情から笑みを消し、一様に真剣な表情でトランペット吹きの方を見つめる。その表情は悲しげでもある。トランペットという楽器が不思議なのか、もしかしたら万々赤という吹き手に因るものかもしれない。笛吹きの少年の有名な絵画があるが、万々赤が頬を膨らませてトランペットを吹く姿は確かにどこか憂いを帯びている気がする。
「万々赤は元吹奏楽部?」
万々赤は小さく首を振る。
「じゃあ何部?」
「俺は野球部。サードで三番、これ如何に」
「聞いてねえし」
「演劇部? 綺麗な顔してるから」
「違います」
「帰宅部だろ?」
「もったいぶるなよ」
三人の視線を集めた万々赤はトランペットのケースをぱちんと閉じると、真っ直ぐに立ち、そして店の中をうろうろと歩き始めた。歩きながら朗らかに「こういう感じです」と言った。万々赤はいつでも爽やかだ。
「やっぱ帰宅部じゃねえか」
「どこが?」
「あ、分かった」
「言ってみろよ?」
「散歩部」
「しょーもな」
「でも近いです」
「もういいわ。飽きたわ。ママは? ママは何部?」
「陸上部」
「激エロ」
「嘘」
「何それ」
「ママはおしっこもしないし、部活もしないの」
「だよね」
「ですね」
わたしは見逃さなかった。万々赤がゴリラの置物を小さく小突いたのを。それは、酔っ払いの下らない会話に苛立って、こっそり物に当たったという感じではなかった。単にゴリラと戯れるような小突き方だった。
ゴリラを小突く部活って何だろう?
「ねえ万々赤、もう一曲吹いてよ。カラオケ無しで」
「もう楽器片付けちゃったんですけど」
「ママのお願いだよ? 俺が払うからさ」
「ううん。私が払うから、そのヒントになるような曲をお願い」
万々赤は考えることもなくすぐに曲が浮かんだのか、可笑しそう「いいですよ」と答えた。
その曲を私達は知っていた。
文房具屋と工務店と私は二千円ずつ万々赤に渡した。